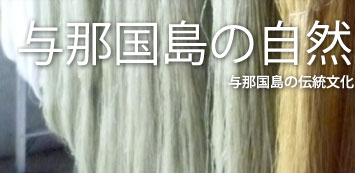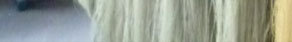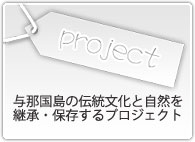与那国島の伝統工芸品|与那国織
与那国島の伝統工芸品|与那国織
 |
与那国島は日本最西端の国境の島です。 この島に生まれた織物には、およそ500年の歴史があると考えられています。16世紀前半頃には既に貢ぎ物として納められていたと考えられます。 戦後の糸が入手しにくい時代には、漁業の網を解いて布を織っていたといわれます。 与那国織は、昔は役人にのみ着用が許されたという幾何学模様の紋織が小花のように可憐な与那国花織、豊年祭などの祭りに着用される与那国ドゥタティ、植物染料で染めた色糸を織りこむ与那国シダディ(手ぬぐい)、ミウト(夫婦)などの絣模様が美しい与那国カガンヌブー、の4つに大きく分かれ、国境の島の豊かな織物文化を今に伝えます。 |
| 与那国花織 | 幾何学的に表現されている花織には、柄によってダチン(八つ)花、イチチン(五つ)花、ドゥチン(四つ)花と呼ばれている。 直線的な構図の中にも伸びやかで広がりがあり、格子縞の織り合わさった色合いがより布に深みを与え美しい花々が元気に咲き誇っているように感じとられる。 どこか優しさの感じられる織物である。 |
| 与那国ドゥタティ | 与那国の方言で4つのことを「ドゥーチ」という。4枚の布を併せて作ることからドゥ(4枚)タティ(仕立て)と呼ばれる。通常着物はみごろの他に、おくみがあるがドゥタティにはおくみがない。昔平民たち普段着として着用していたグバン・ドウタティが反物の名称になったと考えられる。 苧麻や木綿を使用し、衿は黒無地、袖は短く丈も膝下2寸くらいで簡素で涼しいように工夫されている。独特な色使いで必ず白、黒、青を用いて作られており、識別が容易に出来る。 今日でも島内消費が9割を超え、豊年祭や各行事になると島人は皆ドゥタティに身を包む。 |
| 与那国シダディ | 綿や麻地などに福木やシャリンバイなどの草木染、泥染などをした色糸を織り込んでいく、与那国独特のシダディです。 主に祭事で使用されることが多く、女性は頭に巻き、男性は腰に下げる。その他にも舞踊などにも多く使われている。 また米寿を終え亡くなった方の葬式でも用いられ、シダディの意味深さを感じさせます。 |
| 与那国カガンヌブー | 「カガン」とは鏡のことで、「ブー」とは紐を表します。この細帯に織られた模様は男女の愛を唄っています。 中央には夫婦を表すミウト絣(ミトゥダ)の模様があります。主にドゥタティに併せて用いられます。 |
 与那国島の伝統工芸品|民芸品
与那国島の伝統工芸品|民芸品
 |
与那国島の伝統的な工芸品ですが、最近は作れる人が少なくなっています。一言に民芸品といってしまうにはあまりにも数多くの作品があります。 繊細な編みの技法と力強いクバの曲線が相まってなんとも言えない風味をかもし出します。 |
 |
 |
 |
 与那国島の伝統工芸品|草木染め
与那国島の伝統工芸品|草木染め
 |
草木染めは、植物を煮て色素を抽出し染めていきますが、安定させるために、水に溶かした金属と化学反応させて、固着・発色させます。この工程を「媒染する」と呼び、金属の液を「媒染液」といいます。この媒染液の種類によって様々な色に染め上げることが出来ます。 与那国島では、綿や麻地などに福木やシャリンバイなどの草木染、泥染などを施して模様をつけていく。 体験工房などもあり興味のある方には実際に体験してもらえます。 |