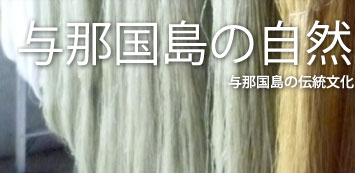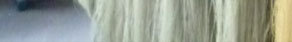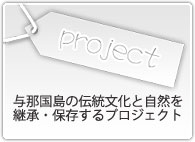島の祭事や行事にまつわる用具
島の祭事や行事にまつわる用具

島では年中行事や祭事、芸能などに使われる、楽器や用具が数多くあり、その呼び名もおもしろい。三線や小太鼓などは一般的だが、その他にも笛やドラ鉦、大太鼓などさまざまである。芸能でも踊りに欠かせない笠や棒、変わったものではイララ(鎌)薙刀、扇子、カゴ、四竹、ちぶんぐ(桴)等がある。
 笛
笛
 |
八重山では笛はフィ、ペーロー、ピーなどと呼ばれています。六孔の横笛で構造は明笛(中国の笛)と似ています。竹製の管で、第1孔から第3孔までを左手で第4孔から第6孔を右手でおさえて吹く。与那国島にいつ頃入ってきたかは不明ですが、おそらく棒踊りと同じ時代であると考えられています。また竹が自生している島であることから、島でも作ることが可能だったと考えられます。 1から12までの笛があり、曲目や奏者の三線などの全体の音色に合わせて笛を選びます。なんとも言えない切ない響きがし、目立つことはありませんが、演奏に無くてはならない楽器です。 |
 三線
三線
 |
沖縄ブームの昨今本土でも三線を弾く方や教室が増えており、三線を知らない人は居ないというくらいです。 与那国島では、芸能や祭事のおりには必ず三線の音色が必要です。八重山の古典や民謡とも少し違う、与那国の古典や民謡があります。 島の芸能の花形であり、繊細にして雄雄しくなんとも言えない味わいのある楽器です。 |
 カニン
カニン
 |
行事ごと、棒踊り、ドゥンタなどの際にリズムとなる1番正確さを要求される楽器。 昔統制と抑圧の厳しかった与那国島において、棒術を鍛錬することは極めて難しいことであった。 棒踊りとして行事の際に踊ることで、島民は役人の目をごまかし棒術の練習に励んだ。そのため笛や太鼓、鉦の音に合わせて踊る事をした。 ンヌンとカニンの合わさったその音色は大地を震わせる、唸りのようにも聞こえる。 |
 ンヌン
ンヌン
 |
ンヌンとは太鼓のことで、その音色は天地を轟かせる激しい響きとされている。 |