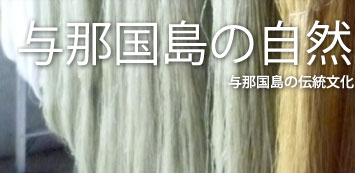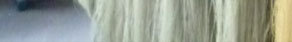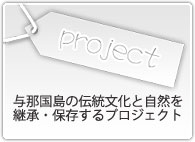青年会によるスルブディ
青年会によるスルブディ

与那国島のエイサーは、明治時代に沖縄本島、読谷の人から伝承されたといわれている。
踊りの激しさや華やかさから最近では盆踊りといえばエイサーと思われがちだが、それよりもずっと古くから、このスルブディは盆踊りとして与那国島で踊られていたのである。
 スル(盆)ブディ(踊り)
スル(盆)ブディ(踊り)
 |
念仏踊りの名の通り念仏に合わせてタスキがけの男女が唄い踊る。勇ましい三尺棒を持った男子と笠を持った女性。踊りの中に見られる手を振り上げたり、払ったりする所作は魔払いであると言う説もある。 この踊りの際に唄われる念仏節は、石垣島で約200年ほど前に作られたとされている。各集落によって念仏の唄は違う。東と西は念仏だが、歌詞の順番や、踊り方が異なり、島仲と比川はかぬやまで踊られる。 三線、太鼓、笛、その演奏者を中央に円陣をつくり、唄い踊る。 祖先崇拝の信仰の厚い島だからこそ、親への敬いや感謝の孝道が唄われている。念仏の意味を知り唄い踊られることで長い間絶やさずに、親や祖先への敬意を今もなお語り継いでいるのであろうか。 |
 |
「スィ。ウッティ、ウッティ、ウッティ」太鼓もちの掛け声でバチを持つ男性が太鼓をたたく。その後ろに3尺棒を持つ男性がいる。 太鼓を持つもの、太鼓を打つもの棒を持つものの3人1組になって踊る。決して派手な踊りではないがシンプルな同じ動作を繰り返す踊りであるだけに、正確さや全体の動作の統一感が重要になる難しい踊りである。 |
念仏の歌詞と意味
| 念仏 | なむあみだぶち あみだぶち うやぬ うぐぬば ふかきむぬ ちちぐぬ うぐぬば やまたかさ ははぐぬ うぐぬば うみふかさ やまぬ たかさや さばかりる あうぎぬかでぃに あうがりてぃ んでぃゆるかたにや ははゆぐてぃ くりふどぅうやに うむわりてぃ ひむとぅぬさがりば きどぅにまて あさんぎぃぬはままでぃ まいらしば さるがてぃやまやま うしばがし うぬゆぬ ゆながに いみうがでぃ にだまにさぐりば んなばない くいするかたにや のひびく しまぬ うらうら みぐりどぅむ すりからやどぅむとぅ たちむどぅり んでぃたる なみだや やしまらぬ すんどむ なにぐとぅ いや うやぬたみどぅしやる |
南無阿弥陀仏阿弥陀仏 それでも何事も 親の為にした |
|
| 念仏 かぬやま | かぬやまてぃらに まいらしば むちゆたるたからゆ まいだしば にしゆんかゆてぃ きゃむんばあぎ ゆみゆたるきゃむんや ちちがたみ するばいてぃゆてぃ たどぅないりば きぬないぬ はちはち するがむぬ はなかきくじきに みでぃすいてぃ ふがまいぬ するする まいらしば うぎとぅい たまわり ぶすとする わがいみ なりゆる いたちくりや |
| かぬやま寺に参らせば ものの哀れな筋なれば 今の三男の造ったもの 持っていた宝を前に出せば 持っていた宝があればこそ 西に向かって経文をあげ 東に向かって経文を読み 読んだ経文は父のため あげた経文は母のため 余りに我が親哀しさに お盆が来て たずねれば お盆は七月中の盆 木の実の初物盆のもの 熟した木の実の数々は飾り物 木の実を上になして供え物 花の絵型の花瓶に水添えて すいすい湧き水を添え水して 身よりの無い霊にお供えし 二人の親のためである 余りに我が親哀しさに 受取り賜われ佛と盆 取差し賜われ父と母 私が夢に見たこと果たしくれば 残ったタミジヤも黴が生え |
 第22回青年文化発表会
第22回青年文化発表会
 |
「〜未来(あす)へ伝える島心〜」をテーマに第22回青年文化発表会(主催・石垣市青年団協議会、青年文化発表会実行委員会)が2008年11月29日、石垣市民会館大ホールで行われた。与那国町青年団協議会も友情出演。 当日の発表会まで二ヶ月前から毎晩公民館に集まっての練習が続いた。島の未来を担う青年会の若者たちの団結力と島への思いがひしひしと伝わってきた。 |