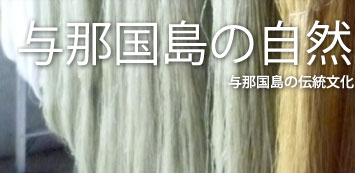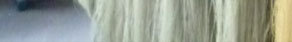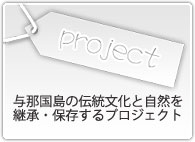与那国島の年間行事
与那国島の年間行事

年間行事
与那国島は日本の最西端に位置し、隔絶された島独特の、特色ある行事、言語がみられ、琉球王朝と南方文化の影響を受けた芸能などが見られる。芸能、文化の多くは今でも冠婚葬祭や、時節に催される行事・祭事で語り継がれ、歌い継がれ、踊り継がれている。
島の祭事は作物の播種から始まり収穫までを一つのサイクルとして、節目ごとに大小30にもおよぶ。
各祭事は神々と島民をつなぐ司(ッカブ)が祭事の日取りから、神への祈願を取り仕切る。近年は司にあたる方(女性が継承)が島外へ移住するなどの問題もあり、後継者が途絶える恐れや、社会の移り変わりによって祭事も形態の変化を余儀なくされているが、地域行事として生活の節目の一つであり、島民の祈りの場であることには今も昔も変わりがない。
そしてその祈りは、家庭や島の繁栄や平和を願うものである。家庭円満・子孫繁栄・無病息災・五穀豊穣・航海安全・海上平穏・大漁祈願等。
島の祭事は作物の播種から始まり収穫までを一つのサイクルとして、節目ごとに大小30にもおよぶ。
各祭事は神々と島民をつなぐ司(ッカブ)が祭事の日取りから、神への祈願を取り仕切る。近年は司にあたる方(女性が継承)が島外へ移住するなどの問題もあり、後継者が途絶える恐れや、社会の移り変わりによって祭事も形態の変化を余儀なくされているが、地域行事として生活の節目の一つであり、島民の祈りの場であることには今も昔も変わりがない。
そしてその祈りは、家庭や島の繁栄や平和を願うものである。家庭円満・子孫繁栄・無病息災・五穀豊穣・航海安全・海上平穏・大漁祈願等。
| 旧朔日・15日の願い | 旧暦の1日・15日 |
| 十山御嶽 | |
| 旧暦の1日、15日は、島民の健康と繁栄を祈願する。 | |
| アラガタトゥタガビ | 旧暦8月の初庚・辛 |
| 与那国島最初の大司(ムトカハマイ)の墓・ナンタ浜から宇良部岳・アラガウガン | |
| 与那国の御嶽の神々を呼び寄せて一年の始まり、今年の島の無事を祈る。作物の播種時期に当たり、島に慈雨を乞い、田畑の稔りを祈願する。 | |
| アラミディ(新水) | 旧暦8月初壬 |
| 宇良部岳麓の田原川上流・アンガイハマティ | |
| ディバルバライとも呼ばれる。一年の初めの祭事で田原川の旧水と新水を取り替える(清掃・祈願)豊年の祈願。 | |
| 牛願い(ウチニンガイ) | 旧2月・旧8月中旬辛丑(各農家や個人はその次の日に執り行う) |
| 旧2月 東・西自治公民館(旧ライスセンター駐車場) 旧8月 東・西自治公民館(屋手久チディの西側) 嶋仲自治公民館(仲嶺牛舎隣り) |
|
| 牛の繁殖の祈願祭。公民館の牛願いと各農家での牛願いがある。 | |
| ダティグクイ | 旧暦8月の丙 |
| 屋手久頂上(ダティグチディ) | |
| 昔は、出船・入船を確認するため、屋手久頂上に拝所を置き、遠見番小屋があった。番人は、船の入・出港の際は、毎夜火を灯し島の場所を示したとされる。今なおこの場所は神聖な場所として毎年旧8月のこの日建て改められて祭事が行われる。 | |
| シティ祭(節祭) | 旧暦8・9月の己亥の日から3日間 |
| 各家庭で行う | |
| このお祭りは悪魔祓いの祈願祭である。その日はンバの葛を家の柱や井戸、庭の木などに巻きつけて厄除けをする。夜は公民館ごとに獅子舞を演じ厄払いを行う。各家庭ではご馳走(フリマイ)を食べ、新しい年を取るされていた。「節」というのは年の区切りの意味を持ち昔は正月の祭りであったとされている。 | |
| クブラマチリ/カンブナガ | 旧暦10月以降の庚申 |
| ミドゥドゥ・クブラビジリ | |
| 異国人・大国人退散の祈願。久部良自治公民館の主宰。 昔、島に外敵が頻繁に襲来し島の食物や家畜などを奪って行くのを防ぐため、この島が巨人の住む島だということを示す意味合いで海に大きな草履を流した。それによって外敵が来襲しなくなったという言い伝えをもとに往時のクブラマチリでは大草履を作って海に流していた。 |
|
| ウラマチリ/カンブナガ | 辛酉(クブラマチリの翌日) |
| ウラマチリトゥニ | |
| 牛馬繁盛の祈願。東自治公民館の主宰。 昔野原家の祖先が山中に居た牛を捕まえ農耕に利用したことから、島で家畜として牛を飼うことが始まった。野原家は牛馬の繁殖も非常に良かったことから同家のウチニガイビディリ(牛願いの拝所)を島の拝所として牛馬の繁殖を祈願するようになった。 祈願終了後一同は祖納家の祈願に参加する。同家では玉、鼓、刀、槍、弓矢などの神器をもち、タマハティと呼ばれる神舞を舞う。 |
|
| ンディマチリ/カンブナガ | 甲子(ウラマチリの3日後) |
| ンディマチリトゥニ | |
| 子孫繁栄・嫁取り・婿取りの祈願。比川自治公民館の主宰。 早朝にアサカダイ(朝のお供え)の祈願がおこなわれその後カダりバクで祈願。後間家でも祈願がおこなわれ、タマハティが舞われる。 |
|
| ンマナガマチリ/カンブナガ | 壬午 |
| 旧島仲村跡の前ヌトゥニ、後ろヌトゥニ | |
| 五穀豊穣の祈願。島仲自治公民館の主宰。 | |
| ンダンマチリ/カンブナガ | ンマナガマチリの翌日の癸未 |
| ンダンマチリトゥニを中心に | |
| 航海安全の祈願。西自治公民館の主宰。 早朝トゥニへ行く途中宇良部岳麓のハイナグで宇良部岳に向かい祈願する。後ろトゥニ東方にあるミドゥディ山でも祈願する。トゥニでは魚を神に捧げる儀式ウブダラナガダラ(大皿中皿)が司、役員、有志などでおこなわれる。祈願の祭事の後は祝宴が催され、トゥニに隣接する与那原家、祖納家の拝所でも祈願がおこなわれる。マチリのフィナーレは、夜になるとドゥンタが始まり、夜更けまで松明を囲みンヌンやカニンの音に合わせて歌い、踊る。 参加者は小屋に籠り一夜を明かす。 |
|
| アンタドゥミ/カンブナガ | ハイナグの霊石(ビディリ)で神分かれ(カンバガリ)ティラクンダで主分かれ(ヌチバガリ)を行う。ここで司達は神衣を脱ぎ、人間にもどる。これで25日間に渡るカンブナガの全日程が終了する。 |
| タナンドゥリ(種取祭) | 公民館役員が各農家に伝達し祭事を行う。家庭ではイハティと呼ばれる稲叢をかたどった大きな握り飯を作り、苗代に献饌する。イニガダニアユが歌われる。 ※米の播種は、在来種米12月、台中米1月、早場米2月。 |
| カドムヌン | 旧暦2月庚辛 |
| なんた港のビディリ | |
|
貢馬619番地で宇良部に向かい祈願。 ハイナグ211番地で宇良部に向かい祈願。 帆安祭の場所の南側190番地でムイムイ(丘)に向かい祈願。 ミドゥディ山拝所1611番地で祈願。 バルミ(割目)1366-1番地でムイムイに向かい祈願。 ウブトゥ(屋手久の南側)1245番地ンサティ大主の墓。 帆安御嶽で祈願。 浦野御嶽で祈願。 最後に、なんた港に来て供え物を出し、取ってきた虫を出して、海に向かい、わが島は小さくて食べ物も少ないからアンドゥの島に行くようにと、これまで持って来た虫を取り出し祈願して海に流す。 |
|
| イスカバイ | 旧暦4月1日、10月1日の年に二回行われる。 |
| 十山御嶽で祈願しその後、我那覇家と東久部良家に行き両家に伝来の船香炉に祈願する。 | |
| この行事の終了によって季節が改まり、この行事の後でなければ、マチリは行わない。春の衣替え、秋の衣替えはその日から始まる。 | |
| ツァバムヌン | 旧暦3月壬(みずのえ)癸(みずのと)の日 |
| 東・西自治公民館(貢 馬) 嶋仲公民館(桃田原橋・旧嶋仲集落) |
|
| 最初に野原家の元家敷から虫を取り、南帆安・北帆安・浦野と巡り北浦野海岸からクワズ芋(ビングイ)の葉で作った舟に乗せて海に流す。 「田草取りも終わり稲が伸びている最中だから虫害がでないように」と祈願する。 その間に各集落の男女が弁当持参で、祖納はナンタ浜に、嶋仲集落はトゥグル浜に、比川集落はカタブル浜に集まり参加者は頭を西に向けて眠り、その間、役員たちは竹の鞭を持って巡り静かにさせ、鶏の鳴き真似をする。これを合図に全員が起きる。この昼寝のことをスディ(払い清める)と言い、スディが終わると各自弁当をひろげ、農事に関する懇談会を行いながら、角力や競馬などを楽しんだ。 |
|
| フムヌン | 旧暦4月庚(かのえ)辛(かのと)の日 |
| 東・西自治公民館(貢 馬) 嶋仲自治公民館(桃田原・旧嶋仲集落) |
|
| 稲穂が出揃う時期であるから、島には旱魃や大風なきよう、島民安泰・繁栄、豊作とともに十日越しの夜雨が降って豊年と豊漁の年が招来するよう祈願する。ツァバムヌンと同じ行事が行われる。 | |
| ドゥガヌヒ(海神祭) | 旧暦5月4日 |
| クブラウガン | |
| 久部良の漁民を中心に行われる、海上平穏、豊漁の祈願をおこなう。久部良の北・中・南の3組対抗のクリ舟によるウガンハーリー(御願ハーリー)転覆ハーリーの競漕がおこなわれその他にも島内の集落全体の競漕なども行われる。漁民最大の行事。 | |
| ドゥムヌムヌン | 旧暦5月の初己亥(つちのとい) |
| 字与那国町49番地の西の北隅、サンバル香炉 | |
| ドゥムヌムヌンはムヌンの最後で、稲の収穫後にねずみやスズメなどの被害がないようにそれらを捕獲してアンドゥの島に送る意味をこめて海に流す。 | |
| アミウリ | 豊年祭の前の吉日。祈願場所は6箇所あり、今年も無事に収穫を終えたので雨が降っても風が吹いてもよいという祈願。 |
| 豊年祭 | 旧暦6月以降の丙午(ひのえうま) |
| 十山御嶽 | |
その年の豊年の感謝、来年の豊年の祈願をおこなう。当日は祈願の後旗頭を参集し、各集落が舞踊や棒踊りを奉納し、東は東・比川集落、西は西・島仲集落の東西に分かれて大綱引きが役場前の大通りナガミティを境にしておこなわれる。 |